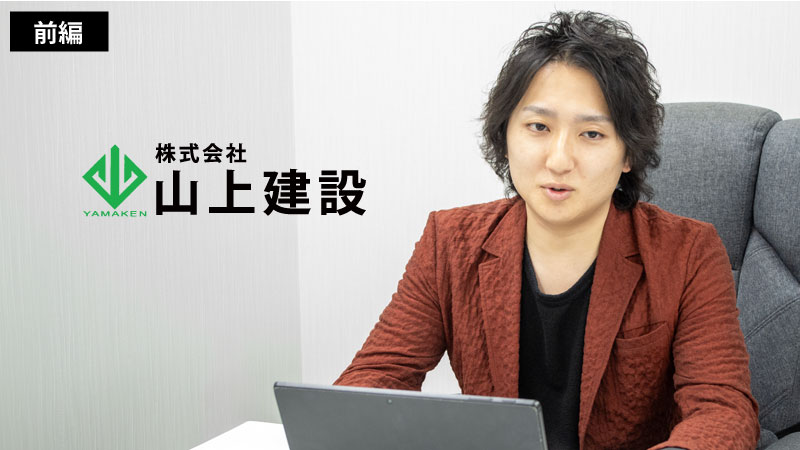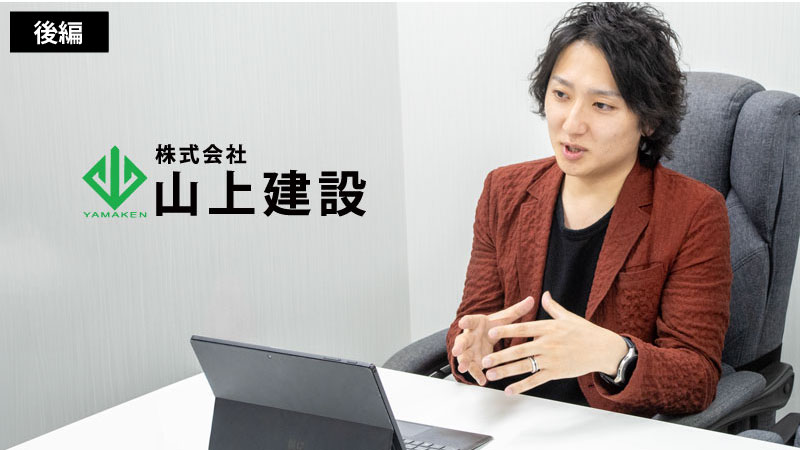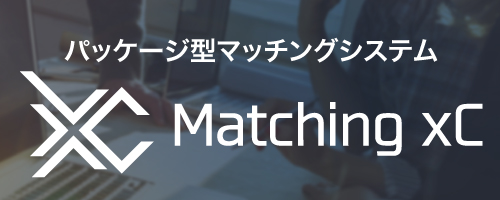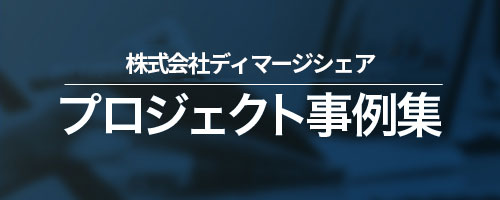【経営者談話】株式会社インサイト社長に訊く
グループ経営と広告ビジネス、
そしてサードパーティとしての
支援ビジネスの在り方


株式会社インサイト

- 株式会社インサイト
- 代表取締役社長
- 紺野俊介 様
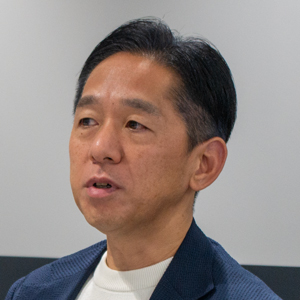
- インタビュアー
- ディマージシェア 代表
- 大内慎
株式会社インサイトは、マーケティング、運用型広告、クリエイティブを中心としたインターネット広告代理店だ。今回、2023年に代表取締役社長に就任した紺野氏に、インサイトグループの事業やデジタル広告・マーケティング市場を切り口に、ベンダーとして事業を支援するビジネスのあり方について伺った。インタビュアーは株式会社ディマージシェア代表取締役社長である大内が務める。

多角化した事業を持つグループのポテンシャルを具体化する
大内) インサイトグループは広告代理業を中心に、今ではデジタルマーケティング全体の支援や、その他の領域まで業務を拡大されていますね。
紺野) そうですね。インサイトグループの事業を大まかに説明すると、広告・マーケティング事業と、いわゆるD2C(Direct to Consumer)事業で、ペットフードやヘアケア商品を取り扱っています。それに加えて『PECHE(ペシェ)』という雑誌の出版事業も行っています。これは自社でコンテンツを作るという文脈上にある事業で、今年度からは雑誌を中核にしたイベントもスタートしています。『PECHE』にモデルとして参画して頂いている方を中心にタッチポイントを作り、様々な人をつなげていくという方針です。
大内) 事業を多角化すると、組織間のつながりや連携が難しくなったりしませんか?
紺野)
一般的には多角化すると事業のサイロ化に繋がりやすいですね。インサイトグループでは現在、グループ間のシナジーを具体化する時期に差し掛かっています。たとえば広告・デジタルマーケティング事業を行っているのに、D2C事業のプロモーションをアウトソースしたりしていて、事業部間のシナジーがうまく発揮できていないところがあったりします。そこを少しずつ変えている、というところですね。
現在、グループ全体でおよそ 140 名ほどの規模です。会社は、ある程度の規模に達するごとに、採用、教育、評価、そして様々なKPIやKGIの再設計を繰り返しながら成長していくものですよね。インサイトグループは、複数の事業がそれぞれある程度の独立性を持って成長してきたので、全体としての統合された設計や意思決定をすることが少なかったという歴史があります。このような組織体には強みもありますが、グループ全体として事業拡大を目指すには、まだ不足している部分が多いのも事実です。ですので、新しいメンバーを迎え入れて強化をしつつ、既存のメンバーとの融和を推進しているところです。
大内) 業務領域を拡大しながら、事業を横串に連携させていく段階ということですね。その段階で、紺野さんが新たに社長として参画されることは、インサイトグループとして大きな節目ですよね。その背景についてお話いただけますか。
紺野)
そうですね。私が参画を決めた経緯について、キャリアを振り返りながらお話しします。元々、新卒で少しエンジニアリングをして、広告代理店である株式会社アイレップに入りました。そこで、当時まだ黎明期だったGoogleの検索連動型広告から、プログラマティック広告、いまの様々なデジタル広告へと進化していく過程を見てきました。
その後、代表取締役として博報堂 DY グループとの組織統合を経て、キャリアのひとつの節目を迎え、次のチャレンジを考えるようになりました。必ずしも広告代理業に限って考えていたわけではありませんが、ファーストパーティとしてデータを持つ、日本で最も大きなプラットフォーマーのひとつである楽天グループが、ちょうど広告ビジネスを大きくしていくタイミングだったので、2018 年から執行役員として参画しました。楽天グループが持っている様々なデータセットや広告インベントリを活用して、広告ビジネスの整理に取り組んだことで、退任までに大きく成長させることができました。

紺野)
今のインサイトでの考え方に繋がることですが、楽天では、グループとして様々なアセットを持っていることや、プラットフォーマーとしてファーストパーティのデータを持っていることのポテンシャルを感じました。事業が連携しあうことで生まれるシナジーを間近で見ることができましたね。
その後、そうしたマネジメントの経験を活かす場を考えていた時に、公私ともに接点があったインサイトの現会長である藤井から、多角化してきたインサイトをさらに拡大させていきたいとお話があり、インサイトグループへの参画に至りました。
大内) なるほど、アイレップや楽天グループで「グループとして経営を拡大する」ことを体感された経験を活かして、インサイトグループでは多角化を維持しつつグループ間シナジーを生み出すことで、全体としてのポテンシャルを底上げすることに注力されているんですね。
『広告業は、本質的にはローカルビジネス』
大内) インサイトグループの広告・デジタルマーケティング事業の一翼を、当社は開発として担わせてもらっています。紺野さんは広告の黎明期からみていく中で、インサイトグループとしてどう成長させていこうと考えているのでしょうか。
紺野)
GAFAMのような巨大プラットフォームと同じ領域を、当社のような規模感の会社が戦うのは現実的ではないと思っています。また、そうした大手プラットフォーマーはグローバルに事業を展開していますが、広告業は本質的にはローカルビジネスですよね。ユーザーがそこに実在していて、言語があって、商品の流通がそこに存在していて、ユーザーのタッチポイントとしてのメディアはローカルに存在していて……。
そう考えると、私たちがやるべきことは「日本というマーケットに最適化するサービスをどう実装していくか」です。当社の強みはクライアントとの深い関係性にあり、既存のクライアントに対してより高度なサービスを提供することに注力しています。
また国内で見れば、総合代理店としては既に大手上場企業が、全方位で様々な業界とのお取引をしています。そうした大手代理店さんは事業規模が大きいため、たとえば、中小規模のクライアントさんに対してはリーチしづらかったり、バリューが出しづらかったりする面もあるはずです。そういった領域が、我々がビジネスとして相対すべき場所だと思います。

大内) 先ほどGAFAMに言及されていましたが、彼らを中心にどんどん新しい技術が出てきていますよね。最近は生成AIをどうやってマーケティングに使おうか我々も考えていますし、そういうお問い合わせも増えています。インサイトグループとしては、そうしたテクノロジーで注目しているものはありますか?
紺野) 昨今は、主にクリエイティブ領域で生成 AIの話も出てきていますが、まだプライバシー保護や著作権管理の問題、いろんな課題が存在している中で、各社が試行錯誤しています。先ほど、インサイトグループでは既存のお客様へのサービス提供をより高度にしていくと言いましたが、まず我々が現実的に始めるべきところは、まさにいまお客様に対して提供している様々なマーケティング施策を、生成AI を活用してより高度なものにしたり、これまでは「人」では実現できなかった施策を実現したりしていくことだと思います。
これからのサードパーティとしての在り方とは
大内) 我々はSIerの会社ですが、インサイトグループの広告事業とは「サードパーティとしてお客様の事業を支援する」という点では共通していると思います。 先ほどの生成AIのように、先端技術を誰もが扱える、ある意味で大衆的なものになったことで、内製化を指向する企業は増えてくると思いますが、ユーザー企業とサードパーティであるベンダーはどのような関係になっていくとお考えでしょうか?
紺野)
まず、アウトソーシング先としての業務については変化を免れないと思います。
当社が支援する広告業務で言えば、単純に広告枠を買って運用するような作業については、いずれAIをはじめとした自動化に淘汰される可能性はあるでしょう。事業会社にとって広告業務は突き詰めればコストセンターなので、可能なのであれば自動化でコストを圧縮しようと考えるのは自然なことです。ただ、クリエイティブやセールスプロモーションのような複合的領域では、どうしても人の手でアナログにやらなければならない部分があります。内製するとした場合、そうしたアナログ部分のリソースを自社で保持し続けるという意思決定は難しいんじゃないでしょうか。全ての広告主が全ての業務を内製化することが難しい以上、現在の広告代理店の業務は、ある程度は残るでしょう。
別の観点では、ノウハウの維持としてアウトソースをする……という考え方はあると思います。マーケティングに限らず、多くの業務にはどうしても人のノウハウに依存する部分があり、いかに仕組み化されているとしても、ノウハウの比重をゼロにすることは困難です。もし事業規模が大きくて、何十人も抱えているような組織であれば別ですが、中小規模の組織であれば人材の流動によってノウハウがリセットされるリスクを常に内包しています。そのため、ある一定の役割をアウトソースしておくことで、ノウハウの水準を維持し続けるというメリットはあると思います。

大内) 最初におっしゃったように、単純な労働力をアウトソースするだけのサードパーティとしての役割は、厳しくなると思います。 当社にも「システムを内製すべきかアウトソースか」というご相談はよく寄せられますが、全ての企業に内製化できるリソースがあるわけではないので、現実的にはベンダーを利用しながら、サードパーティであるベンダーとどう付き合うか、逆に我々ベンダーとしては、どのように価値を提供できるかを考えていかなければならないですね。
紺野) ベンダーとしては、ユーザー側の事業に寄り添うということは必須ですよね。専門性だけでは事業が成立しないですし、事業に寄り添うだけで専門性がなければ実現性に欠ける。ユーザーに寄り添いながら、専門性を活かして具体的な成果を出すことが求められます。 先ほど挙げた、ユーザー側である事業会社の人材流動とおなじで、ベンダー側も人材やノウハウは流動していくと思いますし、ここの寄り添い方はサービスを継続的に提供するベンダー側の課題なのかもしれません。ユーザー側のゴールは、広告を掲載したり、システムを導入したりすることそのものではなくて、会社の規模拡大や、収益を上げていくことにあると認識しなければならないです。そのゴールを見ないでサービスを提供しても、いわゆる“目的と手段の混同”になってしまうでしょう。
大内) 事業や業務に関する理解がどれだけあるか、あるいは気持ちとして歩み寄れるかがポイントですね。突き詰めると、お客様とのコミュニケーションコストをいかに下げていくかという具体的な問題への取り組みに帰結します。だとすると、たとえばオンサイト型の支援などは今後増えてくるサービス提供の形かもしれないですね。 当社ディマージシェアはお客様のパートナーとして伴走するスタイルですが、やはりコミュニケーションの良さをご評価いただくことが多いですね。
紺野)
事業会社側にその分野に長けた人材が少ない場合は、事業への理解や寄り添いが特に重要ですね。ディマージシェアさんのようなシステム開発であれば、ユーザーである事業会社側がシステムに関する知識に乏しい状況下でプロジェクトを進める時に、たとえば要件定義フェーズだとしたら、ユーザー側から要件を言語化していくことってすごく難しいです。ベンダー側が要件を引き出したり、提案したりする歩み寄りは必要かと思います。
あわせて、ユーザー側は、自社のステージに合った提案をされているか考えることが必要ですよね。過剰に高度なサービスを導入しても、活用しきれなくて無駄にしてしまう。さきほどお話したように、GAFAMなどの大手プラットフォーマーではサービスのスケールが合わない、バリューが出しづらい層が存在することと根本は同じです。
大内) 特にシステム開発では、その視点は重要です。大手顧客しか経験がないSIerだと「過剰」という感覚に乏しくて、大手企業の成功ロジックをそのまま中小のスケールで再現しようとしてミスマッチな提案してしまうこともあります。実際のビジネスは原則論に沿わない事が多いですし、ユーザー側事業への理解に立脚した支援を提案していくべきですね。
紺野) ディマージシェアさんとはお付き合いが長くて、直近のプロジェクトでは、途中から要件をすこし変えながら柔軟な対応もしていただいています。そうした柔軟な動きは、パートナーとしての関係性があるからこそ実現できるものだと思っています。それでもなお、寄り添い方については改善できる余地を見つけられるものだと思っています。既にご尽力頂いているとは思いますが、プロジェクトの規模によって担当する人材のレベルも違うし、事業会社のスキルも異なるので、原理・原則どおりにいかない部分を埋めていくために、ぜひパートナーとして、より近い位置で支援されることを目指して頂きたいです。

大内) 今後、期待するところはそのあたりの歩み寄り・寄り添い方ということですね。我々はSIerとしてテクノロジーについての専門性を高めながらも、よりユーザーに伴走していくために日々ブラッシュアップしていますが、実際の現場では日々、試行錯誤をしています。内製に近い感覚で支援できるベンダーであるために、事業会社さんが安心できるよう関係作りを大切にしていきます。
本日はインサイトグループの近況から、広告・デジタルマーケティング業界についてのご見解、サードパーティとしてのビジネスの在り方に至るまで、幅広くご意見を下さいましてありがとうございました。ディマージシェアがお客様の『ファーストパートナー』として、広告業界をはじめとした様々な業界・ビジネスを支援できるように努めてまいります。